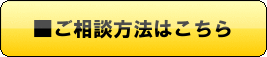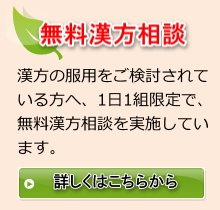不眠症(すっきり眠れない・途中で目が覚める方)の漢方
~漢方で体質から整える~
眠りたいのに眠れない。夜中に何度も目が覚めてしまう。朝すっきり起きられない。
こうした「眠りの不調」は、現代社会で非常に多くみられる悩みです。
厚生労働省の調査でも、日本人の約5人に1人が「睡眠で休養が取れていない」と感じていると言われています。
仕事やストレス、加齢、ホルモンバランスの変化など、原因は人それぞれですが、眠りの質が下がると心身の回復力も落ち、日中の集中力や気分にも影響します。
東次郎薬局では、漢方の視点から不眠症の原因を見極め、「眠れない夜」を根本から整えるサポートを行っています。
不眠症とは? ― 西洋医学と漢方の視点の違い
一般的に「不眠症」とは、
- 寝つきが悪い(入眠困難)
- 途中で何度も目が覚める(中途覚醒)
- 朝早く目が覚めて眠れない(早朝覚醒)
- 眠っても疲れが取れない(熟眠障害)
といった状態が続き、日中の生活に支障が出るものを指します。
西洋医学では、主に睡眠薬や生活指導によって眠りを整えます。
一方、漢方では「なぜ眠れないのか」を体質面から探り、その人に合った調整を行うことを重視します。
漢方からみた不眠症「眠れない」原因
漢方では、不眠は単なる“脳の働きの乱れ”ではなく、「気・血・水」のバランスや「心」「肝」「腎」などの臓腑の働きの乱れによって起こると考えます。
代表的な原因には次のようなものがあります。
・ストレスや緊張による「気滞」
イライラ・考えすぎ・胸のつかえ・頭が熱い感じなどが特徴。
・心と体の疲れによる「心脾両虚」
考えすぎや疲労で心身が消耗し、眠りが浅くなるタイプ。
・加齢や虚弱による「陰虚火旺」
体内の潤いが減り、のぼせ・ほてり・寝汗などを伴うタイプ。
・胃腸の不調による「痰熱内擾」
食べすぎ・飲みすぎ・胃もたれで寝苦しくなるタイプ。
眠れないという表面的な症状だけでなく、「体全体のバランス」を整えることが、漢方による改善の基本です。
よくある不眠のタイプと漢方薬
漢方では、不眠の症状や体質によって以下のように考えます。
精神的ストレス型(仕事・人間関係などで頭が冴えて眠れない)
・「気」を巡らせ、心を落ち着かせる漢方薬
胃腸虚弱型(胃もたれ・お腹の張り・夢が多い)
・消化を助け、心身を安定させる漢方薬
加齢・更年期型(ほてり・のぼせ・寝汗・早朝覚醒)
・体の「陰」を補い、火照りを鎮める漢方薬
体力消耗型(疲れているのに眠れない・動悸・不安感)
・「血」や「気」を補って安定させる漢方薬
※症状や体質により、適した漢方薬は異なります。
実際の処方は、カウンセリングで体質を詳しく確認のうえご提案します。
東次郎薬局の不眠症相談 ― 眠りを支える漢方
当薬局では、不眠や眠りの浅さに対して「体質改善」を中心としたご提案を行っています。
・丁寧なカウンセリング(舌・脈・睡眠環境のヒアリング)
・体質に合った漢方薬のご提案
・食事・入浴・就寝前の過ごし方など、生活養生のアドバイス
長年の経験をもとに、「眠りが自然に訪れる体質づくり」をサポートいたします。
眠りの不調は、単なる「睡眠時間」ではなく、「心と体のバランスの乱れ」としてとらえるのが漢方の特徴です。
ご自宅でできる眠りの養生
漢方薬とともに、生活の中でできる工夫も大切です。
- 就寝2時間前にはスマホ・PCを控え、照明をやわらかくする
- カフェイン・アルコールは控えめに
- 寝る前に軽く体を温める(白湯・足湯)
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 寝る前のストレッチや深呼吸でリラックス
東次郎薬局では、相談時にお一人おひとりの生活リズムに合わせた「養生法」もお伝えしています。
よくあるご質問
Q. 漢方薬はどのくらいで効果が出ますか?
A. 体質や不眠の原因により異なりますが、多くの方が1~3か月ほどで変化を感じ始めます。
Q. 現在、睡眠薬を服用していますが併用できますか?
A. 基本的に併用可能ですが、体調や薬によって異なるためご相談ください。
Q. 一時的な不眠にも相談できますか?
A. はい。季節・環境・ストレスによる一時的な眠りの不調にも、漢方の調整は有効です。
➡ ご相談方法はこちらら